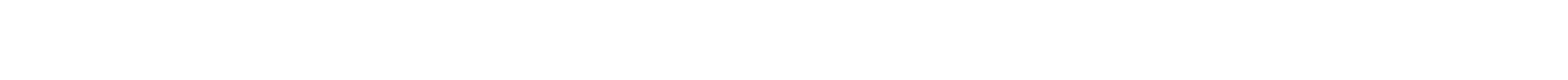落合朗風(おちあい ろうふう)
東京に生まれながらも、生涯平田を本籍とした日本画家である。
落合朗風(おちあい ろうふう)
 朗風は、明治29年(1896)8月17日、東京に生まれ、まもなく母親きくを亡くし父親常市(平田出身)に男手一つで育てられた。朗風は父の出身地である平田を自身の生涯の本籍地としている。
朗風は、明治29年(1896)8月17日、東京に生まれ、まもなく母親きくを亡くし父親常市(平田出身)に男手一つで育てられた。朗風は父の出身地である平田を自身の生涯の本籍地としている。
大正5年(1916)文展に「春なが」が初入選し、早くから注目される。三年後の大正8年には院展に「エバ」を出品、横山大観を感嘆させたといわれる。その後も連続入選するのだが、院展の審査に疑問を持ち脱退。
大正13年から帝展に出品し、再三特選候補にあげられながら涙をのむ。昭和6年(1931)からは、青龍社展に参加。川端龍子と並び賞されるが、昭和9年には脱退し、明朗美術連盟を設立する。
そしていよいよ自らの画境を確立しようとする矢先の昭和12年4月15日40歳という若さで生涯の幕を閉じた。
「おそろしい将来を持つ日本画壇の一人であった。何と言っても早く死なせた事は惜しんでも餘りあることである。」朗風の死を悼んだ藤田嗣治が残した言葉である。
[山湯]:軸装一幅

昭和7年(1932)頃 2400mm×1480mm
本作は、昭和七年開催の第二回個展に出品された「しっかりした手法が全面をよく統整して些の破綻をも見せないのは非凡な力」と報じられた画と同図柄・画題の作品で、同時期に描かれたものと推測される。
幾何学的な線を人物を取り囲む岩肌などに用い、植物や裸体の優美な曲線を強調している。蔓から素足を介して自然と人物へと視点を向けさせる手法、遠近法を巧みに利用しその効果を益すところなど、明らかに西洋画に学んだモダンな構図が今までにない新たな日本画の可能性をにおわす。
カラリストの本領を遺憾なく発揮し、美しい蔦紅葉の中のきらめくような肌の質感が、あたかも聖母を髣髴させる。 朗風作品にはふくよかな女性像が極めて多い。幼くして死別した母の面影を無意識に求めたのだろうか。
[涅槃]:額装一面

昭和7年(1932)第2回個人展覧会出品 920mm×1190mm
本作は、当時、仏画に対する造詣の深さを広く認識させ、近代的解釈を下したと評判となった。本作が出品された第2回個人展覧会を総評する当時の記事はこう報じた。
「中途半端な完成で納まっていられない気持ち、どこまでもやるだけの事をやって見せる気持ち、これが今回の個展で感じられる。この研究的な純情から発した制作だ、悪い感じを受けよう筈がない」この個展の成功が公に認められ、朗風は、川端龍子(かわばたりゅうし)と並ぶ青龍社(せいりゅうしゃ)の作家として確固たる地位を築いていったのである。
特に前年第3回青龍社展に出品した「華厳佛」(けごんぶつ)は画壇に旋風を呼んだ作品であるが、本作はこれに続く仏画の発展の軌跡とも解釈でき、当時の評もおおむねそのように受け止めたものが多い。朗風の父が敬虔なクリスチャンであったことも興味深い事実である。 絹本に描かれた釈迦の安らかな表情、金泥にて丹念に描かれた衣の一本一本の糸に対し、衣のしわ、体の輪郭線などが思い切って単純化されており、対比の妙を示す。
朗風の美的感覚、力量が、その研ぎ澄まされた優美な曲線によってうかがい知ることが出来る。そして、その曲線は釈迦の光背に集約され、神秘的な涅槃図に仕上がっている。
[室内靜物A]:額装一面

昭和8年(1933)第5回青龍社展出品 1815mm×1510mm
朗風自身の言葉「最近静物画に殊に興味が湧いてこの方向にも日本画として進むべき道のあることを信じての一作、一作でこれからも楽しんで大に勉強して行きたく考えている事です。」 第5回青龍社(せいりゅうしゃ)展の当時の美術評を見ると、主宰である川端龍子より、むしろ落合朗風、福田豊四郎らに注目が集まっていることがわかる。
当時の新聞が青龍社の副将格と朗風を堂々と報じるようにもなっていた。この青龍社展で主だった新聞が扱った作品写真は、「浴室」か「室内静物A」など朗風の作品であった。しかし、この年の展覧会を最後に朗風は青龍社を離脱し、翌年、明朗美術連盟を創立するに至る。 美術評は ~物象を美化したものであると同時に黒と白、赤と黒という色の対照とそれを強調づける各種の色の配合、あの装飾的美しさにはちょっとひかれるものがある。
狙いを線においてそれを相当にこなしている点は認めていい。~ と当時評された。この展覧会に朗風はもう2点、「浴室」と「室内静物B」を出品している。特に「浴室」は当時評判となり、現在は国立近代美術館が所有するにまで至っているが、一部には「浴室」より「室内静物A」を高く評価した論評もある。
朗風の青龍社離脱、明朗美術連盟設立を目指す岐路にある頃の作品として、この時期の朗風の作品は近代日本美術史の中でも重要といってよいのではなかろうか。
直線と、曲線を絶妙に配置し、当時の美術評にもあるように極めて対照的な色彩のコントラスト、明らかにキュービズム、シュールレアリズムの影響を受けた革新的、装飾的な本作品の完成度の高さには眼を見張るものがある。朗風の数ある静物画の中でも代表的な作品といえる。
[三瀧観音(遊踪處々の内)]:額装一面
 昭和11年(1936)第3回明朗展出品 1700mm×650mm
昭和11年(1936)第3回明朗展出品 1700mm×650mm
朗風自身の言葉「遊踪處々」(ゆうそうところどころ)について「吾邦土(ほうど)の自然は毎も美しい、私はこの郷土の匂い感覚をとても嬉ぶ、旅をして折々に得た取材を制作に移した、幾十幾百枚でも描いて見たい處(ところ)がありますが、追々(おいおい)の事にしてここでは五作を造りました作品は麻紙の生紙を用ひた。」 「三瀧観音」(みたきかんのん)について「山陽広島市の郊外に三瀧観音と云う霊場があります。
大分俗化されては居るがそれでも翠巒(すいらん)に囲まれて静かな境地です崖に色々の佛像が彫まれている。」 本作品が出品された、第3回明朗展が、朗風最後の明朗展出品となる。(ただし、翌年に明朗美術試作展に出品があるが)よって、朗風晩年の作風を知ることが出来る極めて重要な作品の一つといえる。
伸びやかな筆使いの水墨画風な作品は、朗風晩年によく描かれた。その中でも出来のよい本作品は、朗風の心に残る日本の風景の1つとして描かれている。このころになると朗風独特の線の描き方も自由度を増し、なおかつ確かで、無駄な線がなくなってくる。リズミカルな木々の間からのぞく観音像はのどかで軽やかであるが、それでいて神々しい。