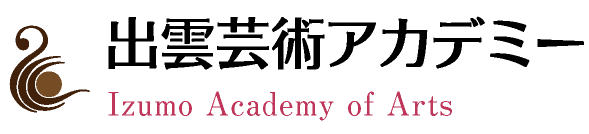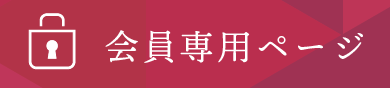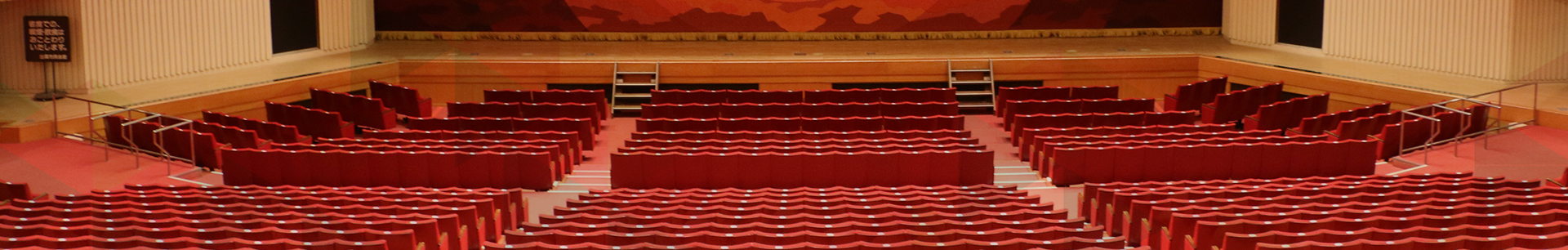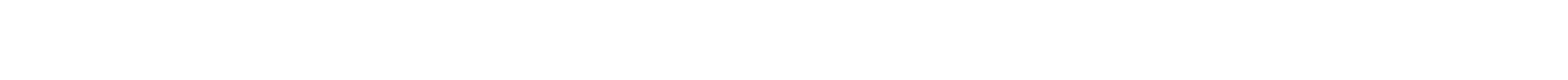マエストロが語る《シルヴァーノ》の魅力 ― 《シルヴァーノ》とはどんなオペラ?
《シルヴァーノ》とはどんなオペラ?
舞台はアドリア海沿岸の小さな漁村。愛、裏切り、嫉妬、赦し――人間の根源的な感情が、祈りと労働が重なり合う信仰共同体のなかで描かれます。
この作品は、《カヴァレリア・ルスティカーナ》の成功を受け、出版社ソンゾーニョから「もうひとつの《カヴァレリア》を」と求められて作られました。台本は同じくジョヴァンニ・タルジョーニ=トッツェッティによるものですが、内容は単なる二番煎じではありません。マスカーニはこの作品で、より詩的かつ象徴的な表現を試みており、海を舞台とした独自のジャンル "dramma marinaresco(ドラマ・マリナレスコ)"=「海辺の民衆劇」という新たな地平を切り拓いています。
- 物語のあらすじ
【第1幕】
青年シルヴァーノは、家族の生活を支えるため密輸に関わり、罪に問われて村を離れることになります。恩赦を受けて故郷に戻ると、かつての恋人マティルデが、漁師レンツォの強引な求愛を受け入れていたことを知ります。
マティルデの心にはなお、シルヴァーノへの想いが残されており、再会によってその感情がよみがえります。しかし、レンツォの嫉妬心が三人の関係に影を落とし、村に不穏な空気が流れ始めます。
シルヴァーノは、かつてふたりで密かに会っていた岩場に来るようマティルデに迫ります。拒めば命を奪うとまで言い放ち、抑えきれぬ激しい想いが行動を突き動かしていきます。
【第2幕】
夕暮れの岩場に現れたマティルデは、レンツォと出会います。レンツォは復縁を求めますが、マティルデはシルヴァーノへの愛を貫く決意を告げます。
その様子を物陰から見ていたシルヴァーノは、怒りを抑えきれず姿を現します。そしてレンツォに「臆病者」と罵声を浴びせたことで、挑発されたレンツォも姿を現し、ふたりは対峙することになります。
次の瞬間、銃声が岩場に響き渡り、物語は悲劇的な終幕を迎えます。
残されたのは、夕闇のなかに漂う静けさと、決して元には戻らない現実。
取り返しのつかない一瞬が、すべてを変えてしまったことだけが残ります。
- 登場人物とキャスト
このオペラには、さまざまな想いを胸に生きる登場人物たちが登場します。彼らの感情は旋律となり、声となり、舞台の上で交錯していきます。歌手たちの一声一声が物語に息を吹き込み、それぞれの人物像を鮮やかに浮かび上がらせていきます。登場人物の行動は「自由意志」によるものというより、「社会的背景」「置かれた境遇」「抑えきれぬ情念」によって駆動されており、これはヴェリズモ文学との強い親和性を示しています。
♠ シルヴァーノ(テノール):
主人公。かつて密輸に手を染めて村を追われたが、恩赦により帰郷。かつての恋人マティルデへの想いを断ち切れず、情熱と葛藤のはざまで揺れ動く。
♣ レンツォ(バリトン):
粗野で激情的な漁師。マティルデに執着し、シルヴァーノとの対立へと突き進んでいく。
♡ マティルデ(ソプラノ):
シルヴァーノの元恋人。彼の不在中にレンツォの求愛を受け入れてしまい、自責と苦悩にさいなまれる。
♢ ローザ(メゾソプラノ):
シルヴァーノの母。息子の帰還を静かに見守りながら、深い愛と祈りを胸に抱く。
- 音楽の魅力と聴きどころ
《シルヴァーノ》の音楽には、まるで海辺に吹き込む風のように、ひとつひとつの旋律が心の奥へそっと染み入るような美しさがあります。マスカーニ特有の繊細な情緒と、ヴェリズモ・オペラに特徴的な激情が、対立することなく寄り添い、ひとつの詩のように流れていきます。
とりわけ第2幕に登場する夜想曲「日は沈み」から舟歌へと至る場面は、その象徴ともいえるでしょう。海のきらめき、黄昏の光、心のさざ波 ―そうした情景がひと続きの旋律となって織りなされ、聴く者をいつしか遠い記憶の岸辺へと誘ってゆきます。
各場面での合唱の用い方には独自の工夫が凝らされており、本作の大きな聴きどころの一つとなっています。女声合唱、男声合唱、混声合唱、そして若者たちの合唱など、さまざまな声が織り成す豊かな響きが、物語にいっそうの奥行きを与えています。さらに、登場人物の心情が交錯する重唱や、マティルデとシルヴァーノによる二重唱では、互いの想いがまるで鏡のように映し出され、感情の揺らぎが美しい旋律に託されていきます。
この作品において、音楽はただ背景にとどまらず、登場人物たちの語りそのものとなります。言葉では言い表せない感情が、音楽となって静かに響き、いつの間にか涙を誘う ― それこそが、《シルヴァーノ》が持つ最大の魅力と言えるでしょう。